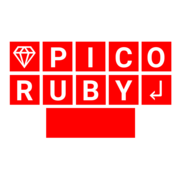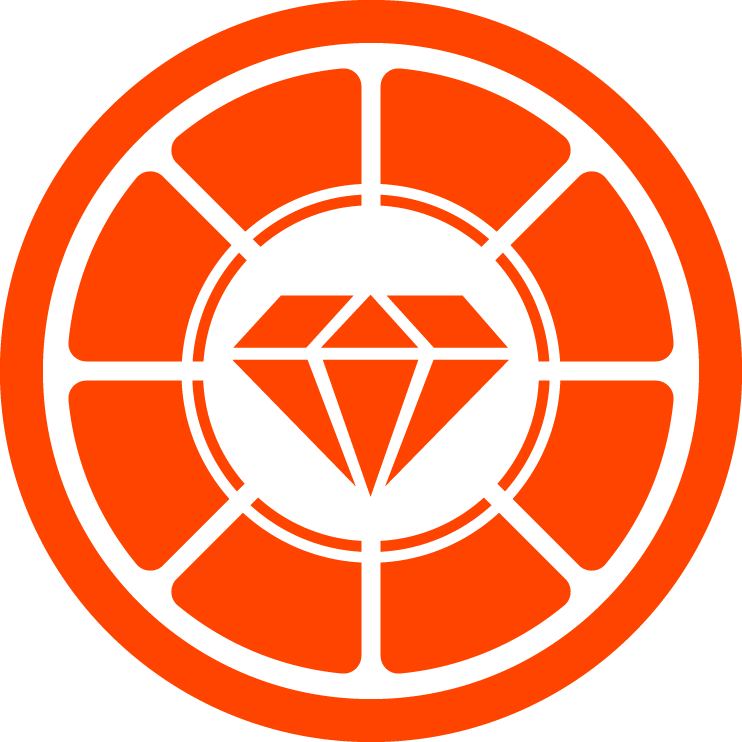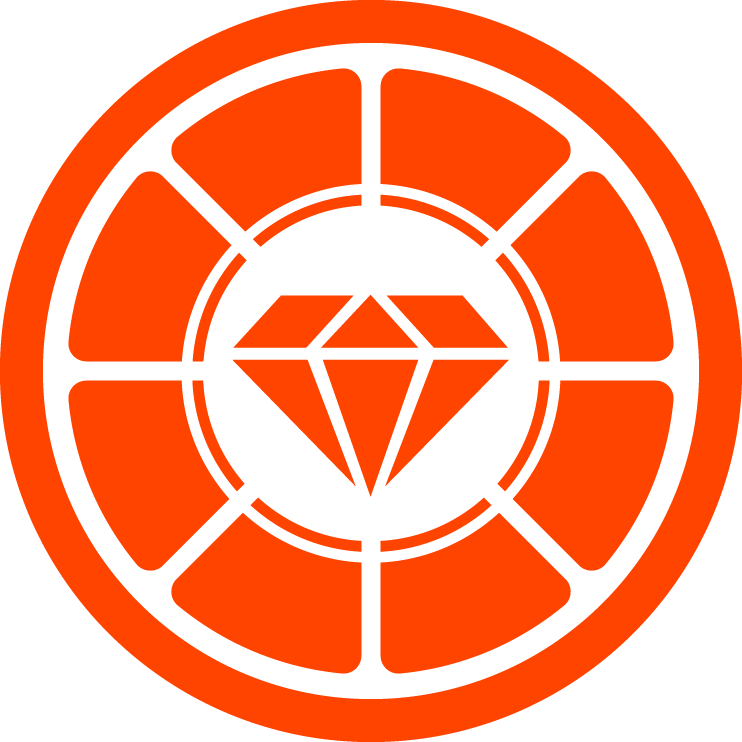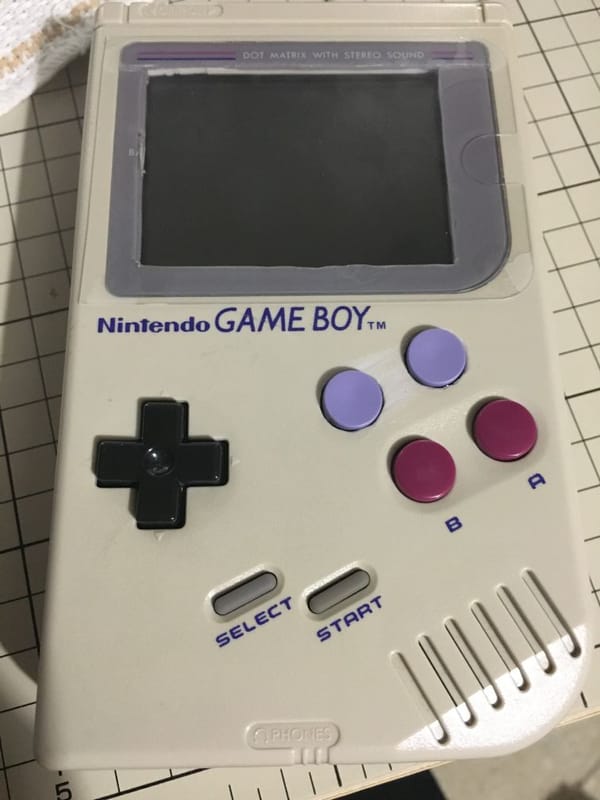PicoRubyを理解する1

ちゃんと中身を理解できてなかったので、コードや資料を読んで理解したい。
特にパーサーやVMの周りをどうやって小さくできているのか。
まずは基礎知識から。
公式情報
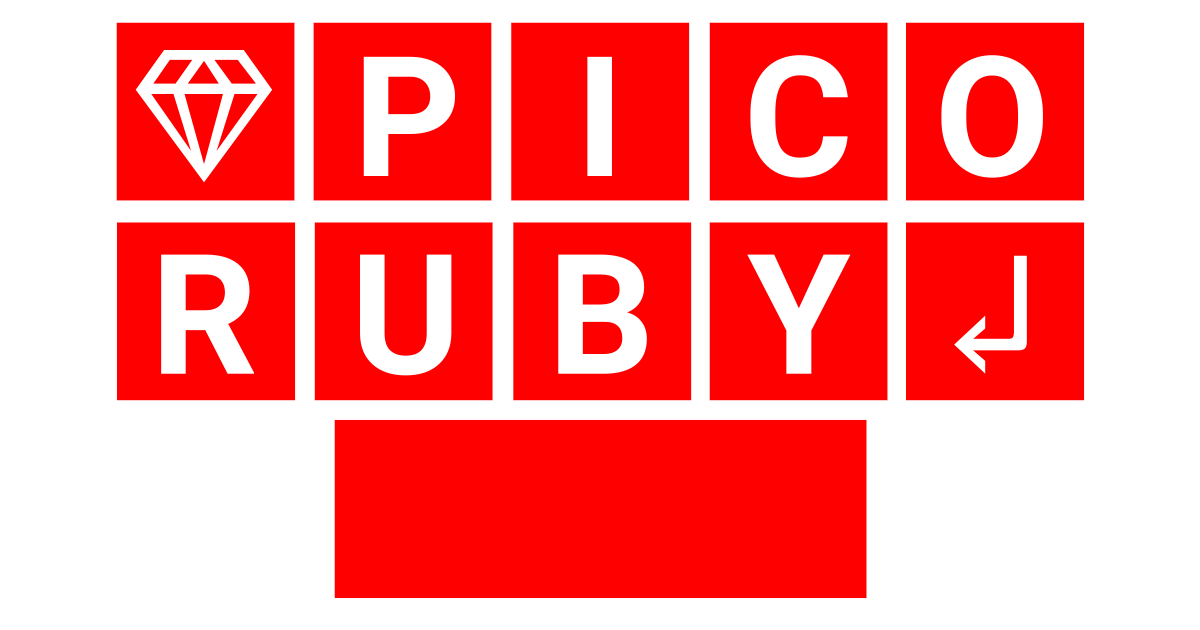
羽角さんの資料
2025

MicroRubyとは?
Ruby会議には参加できてないので、詳細はブログの記事からの理解ですが、以下のような、図のような感じなのかと理解しました。コンパイラをカスタムして準備してしまうのが驚くべきところ。パーサーもPrismに置き換わっているらしい。
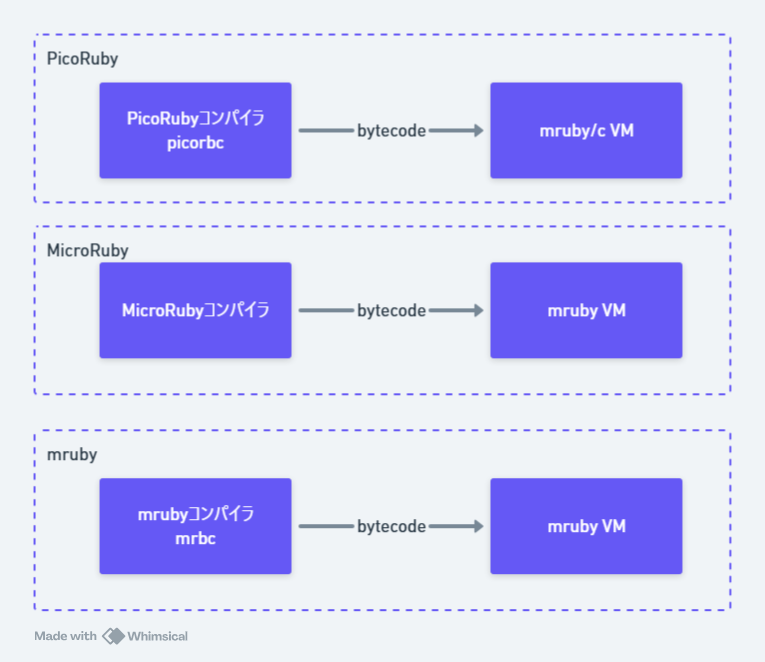
で、コンパイラの周りやmrbgemの扱いなどは、やはりコードを追っていかないといけない。
2024

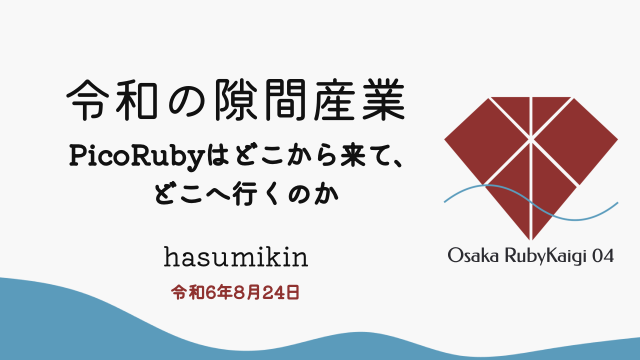
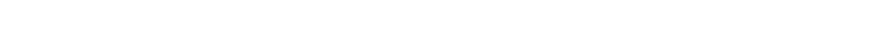
Matz:「そっか、256KBあったらmryubyのVMだけなら動くのか。」
ESP32でPSRAM 8M乗ってるとmrubyのパーサ/コンパイラも込みで動かせた実績あるので、Raspi PicoでもPSRAM搭載ボードなら行けるはず。
羽角さん「僕としては、PicoRubyとかmrubyのエコシステムを広げていくのに、PicoRubyコンパイラを作っただけじゃ面白くなくて、使われないと楽しくないわけですよね。」
とても共感。C書けるなら、Cで書いてしまっても良いのだけど、せっかく環境を作るからには他の人に使ってほしい。羽角さんは一人でエコシステムまで作ろうとしててほんとすごい。

買って読んでみた。
基本的なところからとても丁寧に書いてあるので、PicoRubyちゃんと使いこなしたい方は必読と思いました。
その他

https://www.slideshare.net/slideshow/mruby-c-and-data-flow-programming-for-small-devices/278614229
mruby/cについて、田中先生のスライドが公開されていた。
Node-REDから使えるようにした、というお話。
次のステップ
PicoRubyのコードを読む。